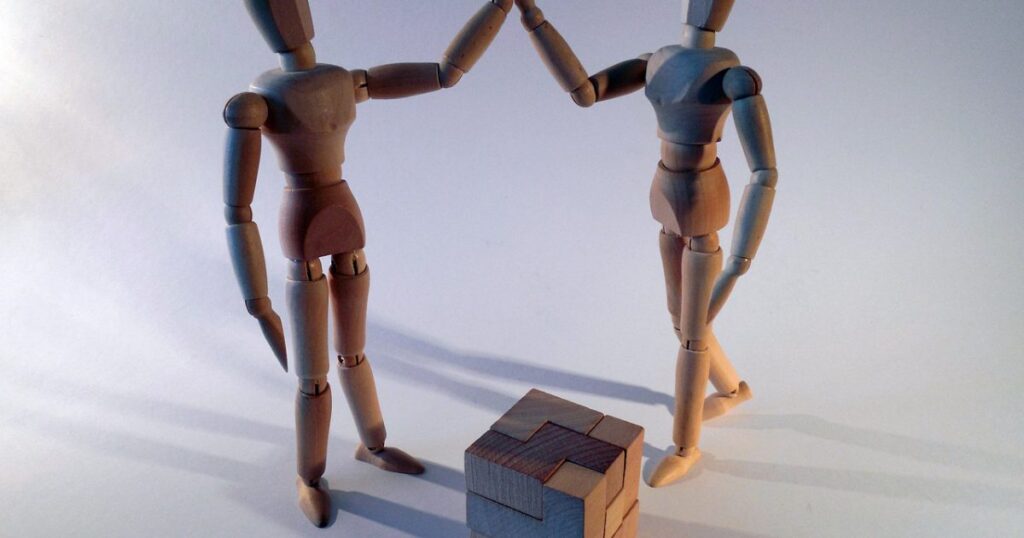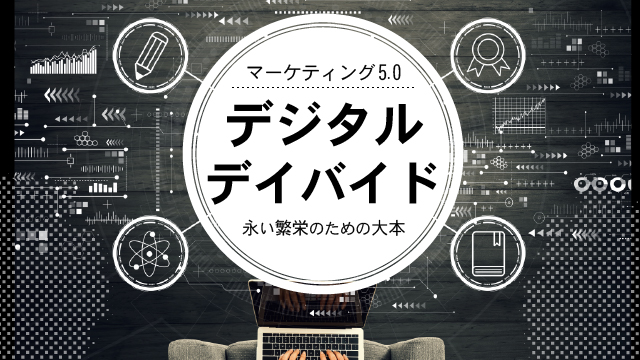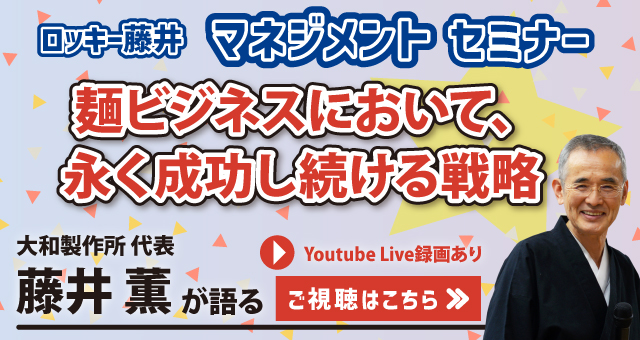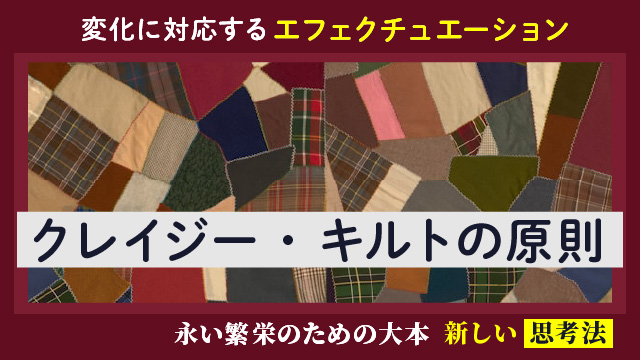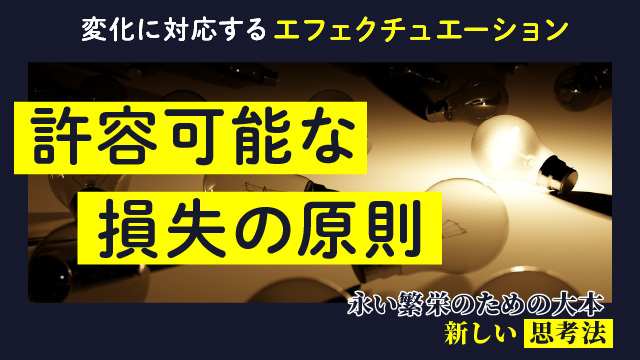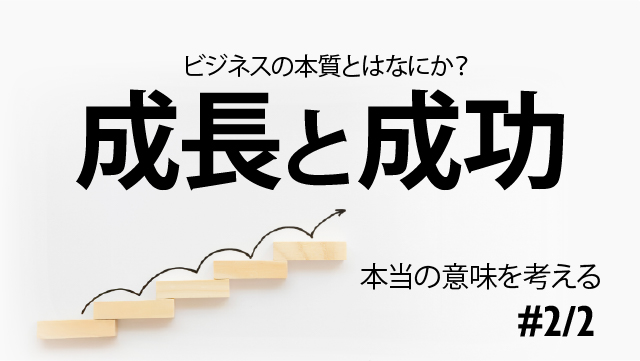ページコンテンツ
はじめに
私が夢中になっているエフェクチュエーションの概念の最期の原則が「飛行機パイロットの原則」です。
私は、過去、飛行機の設計を行なっており、また、飛行機が大好きなので、この原則も非常に納得出来る原則です。
現在のジェット旅客機には、必ずオートパイロット(自動操縦装置)が搭載されて、離着陸を除いては、パイロットは何もせずに、自動操縦装置に任せて飛行を続けることは可能なのです。
それでは、なぜ、パイロットは必ず、2名搭乗しているのでしょう。
その理由は飛行機が常に安全な状態の中で飛行を続けているわけではないからです。
いつ何が起きるか分からない、予測出来ない不測の事態にも安全に飛行を続けるためには、プロのパイロットが2名搭乗しているのです。
何か、不測な事態が起きたときに、即座に判断して危険を回避する必要があるのです。
これはビジネスの世界に起きていることと、同じなのです。
ビジネスを行なっていると、ほぼ、毎日が不測の事態の連続で、飛行中のパイロットのように、常に変化する周りの気象条件、地形、機体の状態、エンジンの状態を確認しながら、飛行機を安全に飛ばし続けなければいけないのです。
従って、パイロットは、コントロール可能な活動に集中し、不測の事態に対処しているのです。
パイロットにとって、コントロール可能な飛行機の機能は、機体が完全な状態である限り、多くの機能をコントロールすることが出来るのです。
ところが、御巣鷹山(群馬県)に墜落したJALの旅客機の場合は、機体に欠陥が発生し、コントロール可能な活動が非常に限定されたのです。
それでもパイロットは残っている機能を最大限に活用し、事故が発生した時点から飛ばし続け、御巣鷹山まで飛び続けたのです。
私は飛行機に詳しいので、その当時の操縦室の緊迫した様子が手に取る様に分かります。
会社経営も同様で、時には御巣鷹山へ向かっているJALの機内のような状態に陥っていることもあります。
そのような場合にも、常に、コントロール可能なことだけに集中し、それ以外は、一切念頭に置かないことです。
熟達した起業家の世界観
①「飛行機のパイロット(pilot-in-the-plane)の原則」
「コントロール可能な活動に集中し、予測でなく操縦によって望ましい成果に帰結させる」という思考様式になります。
「飛行機のパイロットの原則」は、そもそも不確実な未来に対して熟達した起業家が持つ世界観を反映したものであり、下記の4つの思考様式によって駆動されるのです。
エフェクチュエーションのサイクル全体に関わっているものと理解できます。
〇 手中の鳥の原則
〇 許容可能な損失の原則
〇 レモネードの原則
〇 クレイジーキルトの原則
不確実性に対処するパイロットの重要性
予測に基づいた最適な計画の策定を重視するコーゼーションの発想は、起こりえる事態を事前に分析・想定することで、オートパイロットシステムを設計しようとする発想に近いともいえるかもしれません。
そこでは、目的地にたどり着くための計画策定とシステム設計こそが重要で、パイロットはその実行者にすぎません。
これに対して、エフェクチュエーションの発想では、予期せずして巻き込まれた乱気流のなかでも、実行可能で、意味のある行動を意思決定し続ける起業家自身の主体的なコントロールこそが、航空機が飛び続けるために絶対不可欠な条件になります。
想定外の偶然をテコとして活用する「レモネードの原則」や、パートナーの獲得を通じて新たな方向性を共創していく「クレイジーキルトの原則」は、ともすれば行き当たりばったりの他人まかせではないか、という誤った印象を与えるかもしれません。
しかし、そもそもパイロットが、偶然の出来事や出会いを通じて創発する新しい可能性を見逃すことなく、そこから意味のある結果を生み出すために常に操縦桿をコントロールし続けるからこそ、こうした外部環境からもたらされる要素を取り込んで、望ましい成果を生み出していくことが可能になるといえるでしょう。
自らを取り巻く半径2メートルの世界を変える
「飛行機のパイロットの原則」は、他のエフェクチュエーションの4つの原則を組み合わせることで実行されます。
① 「手中の鳥の原則」⇒手持ちの手段に基づいて「何ができるか」を発想する問い
② 「許容可能な損失の原則」⇒現時点での自分がどのような損失を覚悟できるか
こうしてコントロールの可能な範囲で新たに行動を生み出すと、起業家が直接・間接に相互作用を行う人々の中で、周囲2メートルにいるような局所的な他者に対して影響を与えることでしょう。
そして、他者から得られた新たな反応によって、起業家自身の環境へのコントロールの可能性は高まっていくことになります。
こうした行動の結果に対する結果を含めて、さまざまな外部環境の要素を取り込んでいく思考様式が「クレイジーキルトの原則」によって、相互作用をした相手から自発的な意見を獲得できれば、起業家の手持ちの手段と「何ができるか」は拡張し、環境に対するより大きなコントロールの可能性を手にすることができるでしょう。
また、結果として予期せぬ事態が起こった場合でも、「レモネードの原則」によって偶然を機会として活用して新たな行動を生み出すことで、もともとの計画に固執する場合よりも、状況に対するコントロールの可能性を高めることができるでしょう。
このようにエフェクチュエーションのサイクルは、5つの思考様式の実行を通じて環境に対するコントロールの可能性を徐々に高め、その結果として取り組み全体の実効性を高めていくプロセスなのです。
パイロットが有効に機能する問題空間
オートパイロットシステム(コーゼーション)とパイロット(エフェクチュエーション)の両方を活用できる場合、どのような問題がパイロットでなければ対処できないといえるのでしょうか。
エフェクチュエーションがとりわけ有効に機能する問題空間には、大きく3つの特徴があると考えられています。
① 未来の結果に関する確率計算が不可能である
「ナイトの不確実性(Knightian uncertainty)」⇒結果について確率の判断が不可能な状況
② 選好が所与ではない、もしくは秩序だっていない
「目的の曖昧性(Goal ambiguity)」⇒矛盾した複数の目的を持っている。
目的が不明瞭であったりするために、秩序だった目的に基づいた首尾一貫した選択を行うことが困難な状態
③ どの環境要素に注目すべきか、あるいは無視すべきかが不明瞭である
「環境の等方性(Isotropy)」⇒意思決定や行動するうえで、環境に存在する情報が注目に値し、どの情報が賢明な判断につながるかが、必ずしも事前にはわからないような状態です。
コーゼーションとエフェクチュエーションの使い分け
コーゼーションとエフェクチュエーションは、どちらか一方があらゆる状況で有効であるわけではなく、両方を状況に応じて使い分けるべきであるといえます。
コーゼーションとエフェクチュエーションの関係については、【サラスバシー】が最初に発表した論文のなかでも、「コーゼーション的推論とエフェクチュエーション的推論は、常に逆方向に作用するわけではなく、むしろ両者は補完的に機能する」ことが指摘されています。
ただし、こうした環境の変化に応じて意思決定に活用される論理が自然と変化するわけではなく、エフェクチュエーションとコーゼーションの両方を理解したうえで、意図的に切り替える能力が重要であることも指摘されています。
エフェクチュエーションとコーゼーションの組み合わせについては、今後の研究を通じてより理解が深まっていくことが期待されます。
ただし一方で、豊富な経験を積むにつれて、起業家自身はますますエフェクチュエーションに熟達し、好んで用いるようになることも想定されています。
不確実性を伴う挑戦においては、環境の変化から目を離すことなく自ら操縦桿を握って対処し続けることが重要であり、そうすることによって起業家は、熟練したパイロットのように、どのような不測の事態でも経験によってより望ましい結果へと導いていけるようになるのです。
それでは、次に、エフェクチュエーションの全体プロセスを活用して成功した事例を見ていきましょう。
世界中の人々が宿泊する〝氷のホテル〟はどのように生まれたか
アイスホテル
北極線から北に200㎞の位置にあるスウェーデンのユッカスヤルヴィという人口700人の小さな村に、12月から4月の冬の間に作られる「アイスホテル」の事例です。
アイスホテルは、その名の通り、ほぼ全てが近くを流れるトルネ川から切り出した氷と雪で作られたホテルで、春には消えてなくなるため、翌11月に再び新しいデザインのアイスホテルが作られます。
アイスホテルは、ユッカスヤルヴィという地域ならではの自然環境を資源として活用した観光事業の成功事例であり、近年注目を集めるサスティナブル・ツーリズムの先駆けともいえるでしょう。
しかし、生み出された時点では、起業家自身を含む誰1人として、こうした事業機会を見通していたわけではありませんでした。
趣味から始まったラフティング体験事業
アイスホテルを創設したのは、イングヴィ・ベリークヴィスト(Yngve Bergqvist)という青年でした。
彼は、毎週末ユッカスヤルヴィを流れるトルネ川でラフティングをすることで、仕事のストレスを解消していました。
ある日、通りすがりの観光客からボートに乗せてほしいと頼まれたことをきっかけに、ラフティング体験を提供することがビジネスになるのではないかと考え始めます。
そこで、観光案内所で働く知り合いに相談をして、毎週末の朝に観光案内所を訪れる観光客に、ラフティング体験を提案するという行動を始めます。
もし仮に利用客が獲得できなかったとしても、イングヴィ・ベリークヴィストが失うものはほとんどなかったといえるでしょう。
実際には、行動の結果は期待以上のもので、彼はほぼ毎回の利用客を獲得し、
そこから安定した収入も得られるようになりました。
そしてラフティング体験の事業が軌道に乗って初めて、彼は鉱山会社での仕事を辞めて、仲間とともにカヌーセンターを起業し、夏季には40名の従業員と30のボートを抱えるまでに事業を拡大させます。
不測の事態と冬の観光資源の探索
短い夏が終わり冬になると、川は堅い氷に覆われてしまうため、ラフティングはできません。
スウェーデン北部の極寒の冬は、光にあふれた短い夏とは対照的に、暗く恐ろしいものという認識が強く、地元の観光業者でさえ冬の誘客は不可能と考えていました。
それでも、「足元を掘れ、まだまだできることがある(Dig where you stand‐much still remains undone.)」をモットーとする彼は行動し続けます。
すると冬の北極圏には、オーロラを観測するために日本人観光客が訪れていることがわかりました。
そこで東京のスカンジナビア観光局にツアーを企画する旅行会社の情報を求め、行き着いたのがサカタ氏でした。
サカタ氏との出会いをきっかけにスウェーデン北部にも日本人観光客が訪れるようになり、日本には、冬に全国から多くの観光客を集める「さっぽろ雪まつり」というイベントがあることを教わります。
そして1988年にさっぽろ雪まつりの会場を訪れたイングヴィ・ベリークヴィストは、巨大な氷像・雪像とそれを見に押し寄せた多くの観光客を目のあたりにしました。
雪と氷であれば、自分たちの地域にもっとふんだんにあると考え、またホテルで出会った旭川市出身の氷の彫刻家とも意気投合した彼は、ユッカスヤルヴィで冬に、より大規模な氷の彫刻のアートフェスティバルを行うという構想を描きます。
翌冬に2人の日本人アーティストをユッカスヤルヴィに招いて氷や雪といった素材の扱い方を学び、また氷の彫刻をつくる国際的なアーティストの関心も惹きつけ、複数のメディアの取材も受けました。
それまで冬の観光資源が何もなかったユッカスヤルヴィには、氷や雪で作られた見事な彫刻作品が並び、欧州中から観光客が詰めかけることになりました。
計画通りでなかった氷のアートフェスティバル
イングヴィ・ベリークヴィストの家族や村の人々は、美しい氷の彫刻が完成する様子に感動し、翌朝の開催に心を躍らせていました。
しかし、当日想定外の事態が起こります。
翌朝6時に目覚めたイングヴィ・ベリークヴィストが耳にしたのは、不穏な音でした。
外に飛び出すと、その地域では冬にほとんど観測されたことのない雨が降っており、気温は7度に上昇していました。
最悪の事態に怯えながら会場に向かうと、スタッフたちが雨を凌ごうとアート作品の上にシートを広げて、イングヴィ・ベリークヴィストに指示を求めました。
すでに観光客やメディアが多く集まる会場で、その日のために準備をした作品が崩れかかっている最悪の事態でした。
その時彼は、再び自らの本質に立ち返ることになりました。
彼は自然が大好きで、だからこそ環境エンジニアの仕事や、ラフティング体験の提供、トルネ川の氷と雪を活かしたアートフェスティバルを企画してきました。
そして、自分が「自然は人間の思うようにならない、だからこそ面白い」と考えていたことを再認識したのです。
彼は己を奮い立たせて、スタッフに伝えました。
「壊れるに任せよう。それが解けてしまったら、その時に何か新しいものを作ろう」
フェスティバルの会場には、氷を削り出すための道具と技術を持つアーティスト、来場した多くの人々と、豊富な雪と氷がありました。
イングヴィ・ベリークヴィストたちは、氷の彫刻を作る道具を手にすると、人々にアプローチしました。
来場者にも氷を削り出す技術を教えて、一緒に新しいものを作り出すワークショップを提案したのです。
参加したグループは氷の彫刻を作る技術を学び、他のグループは氷のブロックを積み上げて「イグルー」(北極圏の住民が作るドーム型の簡易住居)を作り始めました。
夜になったとき、イグルーを完成させたグループが、そのなかで一夜を明かそうと、他の人々を招き入れました。
入ってみると氷のドームによって外気が遮断されたイグルーの内部は、意外にも寒くも暗くもありませんでした。
むしろ半透明の氷を透過して入ってくる光が揺らめいて、幻想的で夢のように美しい空間だったのです。
氷のアートギャラリーからアイスホテルへ
結果として、氷の彫刻のアートフェスティバルは失敗に終わったものの、氷の建物を作る新しい技術を習得し、イグルーのなかで素晴らしい経験をともにしたグループは、翌年以降もユッカスヤルヴィに集まって活動を継続しました。
1990年には、250平方メートルの円筒形のイグルーのなかで、フランス人アーティスト、【Jannot Derid】のアート展が開かれました。
イグルーは、「アーティック・ホール」と名付けられ、何百人もの来場者が氷で作られたアートギャラリーを訪れました。
また同時期に、海外から来たゲストが、キルナで開催中の全国スキー選手権のためにホテルが満室で泊まれなくなる。
というハプニングも起こります。
イングヴィ・ベリークヴィストはアーティック・ホールでの宿泊を提案し、承諾したゲストが寝袋とトナカイの毛皮で一夜を過ごしたところ、それは想像よりもずっと快適で魅了されるような体験でした。
そこからアイスホテルのアイデアが具体化していきました。
1992年から1993年にかけて、最初の本格的なアイスホテルが建設され、イングヴィ・ベリークヴィストと仲間たちは、アイスホテルABという会社を設立しました。
10月末から始まるアイスホテルの建築では、まず地元のアーティストや建築家が建物全体の構造を作ります。
建材には、自然の雪と氷に加えて、snice(スニス:snow+iceの意)」と呼ばれる機械で作られた雪も使用されるようになり、
春になっても屋根が崩れることのない、アーチ型の鋼鉄製の型枠をベースにした構造が開発されて特許も取得しました。
建物がほぼ完成すると、スウェーデンの国内外から集められたアーティストが、窓やドア、柱、家具、ランプ、そしてさまざまな彫刻を含む内装を、独自のスタイルで制作します。
1つ1つの部屋自体が氷のアート作品であり、多くの訪問者を惹きつけるアイスホテルの大きな魅力になっています。
1992年には氷のチャペルも建設され、年間約150件の結婚式と20件ほどの洗礼式が行われ、2006年には通算第1000回目となる結婚式が執り行われました。
こうしたアイスホテルの事業規模は、やがて夏のラフティング体験事業を超える規模にまで成長します。
アブソルート・ウォッカとのパートナーシップ
アイスホテル内に作られたアイスバーが、その後、世界各地にも展開されることになった経緯には、スウェーデンを代表するウォッカブランド「アブソルート・ウォッカ」との重要なパートナーシップの構築がありました。
イングヴィ・ベリークヴィストはかねてから、海外からの観光客が訪れるアイスホテルと、スウェーデンを象徴する「アブソルート・ウォッカ」と結び付けたいと考えていました。
当初提供企業は、まったく関心を示しませんでしたが、アイスホテル内にはすでに1994年からアブソルート・ウォッカを飲めるアイスバーが設置され、そのメインの装飾は、巨大なアブソルート・ウォッカのボトルを模った氷の彫刻でした。
イングヴィ・ベリークヴィストたちは、プロカメラマンが撮影したアイスバーの写真を使ったプレスリリースを米国とドイツの各1000社に送付し、それが掲載されたメディアが提供企業の目に留まり、ようやくパートナーシップの可能性が見出されます。
同社は、まずは数名のスタッフをユッカスヤルヴィに派遣して、アイスバーのスポンサーになることを決め、共同のプロモーション活動を開始します。
1997年には、イタリアのファッションブランド「ヴェルサーチ」と「アブソルート・ウォッカ」とのコラボレーションキャンペーンによる広告が国際的な注目を集めました。
その広告では、ナオミ・キャンベル、ケイト・モス、マーカス・シェンケンバーグといったトップモデルが、「アブソルート」のボトルをイメージした「ヴェルサーチ」のデザインを身にまとい、マイナス27℃のアイスホテルを舞台に撮影された写真が話題を呼びました。
その後も、ボルボの米国向けのテレビCMやジェームズ・ボンドの映画など、さまざまな撮影のロケーションとしてアイスホテルが使用されるようになり、現在では毎年600〜700のメディア企業がアイスホテルを訪れています。
パートナーがもたらしたビジョンによる世界的展開
ただし、「アブソルート・ウォッカ」とのパートナーシップは、ベリークヴィストたちが当初思い描いていたよりも、ずっと大きなビジョンをもたらすものでした。
この世界第4位のスピリッツ・ブランドは、アイスホテルと共同で、トルネ川の氷を使ったアイスバーを世界中に展開する、という構想を描いていたのです。
まずは、2002年6月にストックホルムにパイロット・プロジェクトとしてアイスバーが作られ、その後に年間常設のアイスバーになりました。
アイスバーの室内は-5℃に保たれ、50トンのトルネ川の純度の高い氷を削り出して、バーカウンターやテーブル、ソファ、グラスなどが作られます。
2007年には、年間10万人の人々が銀色のポンチョを着て、トルネ川の氷でできたグラスでウォッカのドリンクを飲む、ストックホルムで最も収益性の高いバーとなりました。
アイスホテルと同様に、アイスバーのデザインも国際的なアーティストが招待されて、6か月ごとに作り直されます。
ストックホルムを皮切りに、2004年にロンドン、東京、ミラノ、2007年にはコペンハーゲンと上海にもアイスバーがオープンし、いずれの店舗も、「トルネ川からの80㎡の氷で作られたバー」という同じコンセプトの下で運営されています。
解けてなくならないアイスホテルの建築
こうしてアイスホテルが有名になると、次第に、ユッカスヤルヴィを夏に訪れる観光客のなかにも、アイスホテルへの訪問を期待する人々が増えていきました。
そこでイングヴィ・ベリークヴィストは、パートナーシップの拡大を模索し、
夏季に約100日間続く白夜を利用した太陽光発電で電力をまかない、夏にもアイスホテルが解けないようにする、という発想に至ります。
そこで建築家のハンス・イークがこのプロジェクトの主任建築家となり、氷と雪で作られた20部屋のスイートルーム、アイスバー、アイスホテルの歴史を学ぶことのできる体験ルームからなる、2100平方メートルの巨大な建築物の着工がなされました。
5か月をかけて、全ての電力が太陽光発電によってまかなわれる、まったく新しいアイスホテル「Icehotel 365」が完成し、2016年11月に最初のゲストを迎えました。
夜はホテル、昼は雪と氷のアートギャラリーとして365日オープンする施設ができたことによって、人々とトルネ川との関係も、より強固なものになりました。
夏にアイスホテルを訪れた人々には、その建物の元となるトルネ川の水を、ラフティングでも体験してもらうことで、より一貫した忘れがたい経験を提供できるようになったのです。
「非予測的コントロール」によって存在しなかった市場が紡ぎ出される
これまで確認してきたアイスホテルの事例から、最初の時点で、起業家に明確な目的や事業機会が見えている必要は必ずしもありません。
重要なのは、そうした予測を超えた外部環境の意見を得たときに、それに翻弄されたり、逆に事前の予測や計画に固執して見過ごしたりするのではなく、その場・その瞬間でコントロール可能な活動に集中して、パイロットとして対処する行動をとることであるといえます。
そうして新たな行動を生み出すからこそ、危機的事態や新たな他者との出会いを含む、外部環境における偶発性を自らのコントロール可能性を拡大する機会として取り込んで活用することが可能になります。
5つの原則を統合してエフェクチュエーションのサイクルを回す
起業家は、自らの本質や知識、社会的なつながりに基づいて着手する「手中の鳥の原則」と、起業家自身の可能なリスクテイクを反映した「許容可能な損失の原則」に基づくことで、未来の結果が予測できないような不確実性の下でも、起業家自身にとって意味のある一歩を合理的に踏み出すことが可能になります。
ただし、それだけでは実行可能性とリスクへの対処を重視した、小さな行動にしかならない恐れがあるでしょう。
そうした行動が、新たな市場や事業機会を含む、より大きな価値の創造につながりうるのは、行動を起こして初めて得られる、外部環境からの感想(予期せぬ結果や、人や情報との出会い、制度的障壁など)を起業家が取り込み、より実効性の高い行動へと繰り返しアップデートするためです。
こうした対応を可能にする思考様式が、「クレイジーキルトの原則」と「レモネードの原則」であると理解できます。
最後に「飛行機のパイロットの原則」は、こうした外部環境との相互作用を含むプロセスの全体を、起業家自らがコントロールしようとする主体性に関連するといえます。
偶発性にどのように対処するのか、誰がパートナーとなり誰がそうならないのか、といった意思決定は、パイロットである起業家自身によってなされるのであり、そうした意思決定には「私は誰か」という本質が強く反映されると考えられます。
エフェクチュエーションのプロセスにおいて、行動の起点となる手持ちの手段(資源)の筆頭に「私は誰か」という本質に関わる要素が挙げられるのは、結果が予測不可能であるゆえに最適な行動が定義できない不確実な意思決定においても、本質こそが「何をすべきか」を判断する一貫した指針を提供しうるためです。
そして本質は、最初は起業家自身の「私は誰か」と同一であるものの、エフェクチュエーションのサイクルが繰り返してパートナーが獲得される結果、徐々に「私たちは誰か」という組織的なアイデンティティが形成されると想定されています。
逆にいえば、起業家やそのチームの本質にそぐわないために、対応が見送られた予期せぬ事態やパートナー関係も、当然ありうると考えられます。
このように、エフェクチュエーションを構成する5つの思考様式は、それぞれが単独で活用されるわけではなく、お互いに影響し合う関係にあります。
これら5つの思考様式の補完関係を意識しながら、エフェクチュエーションのサイクルを回し続けることによって、起業家であるあなた自身の内部環境(起業家自身の認知や感情、願望など)と、外部環境(市場構造や制度、さまざまな利害関係者など)の状態を反映した、新たな価値を形にする実践が可能になると考えています。
飛行機のパイロットの原則のまとめ
飛行機のパイロットの原則では、コントロール可能なものだけに焦点を当て、
コントルール出来ない外部環境には、一切予測もせず、関与もしないということでした。
そして、手中の鳥の第1原則から始まるエフェクチュエーションでは、自分が既に持っているものを最大限活用することから始まっていました。
これは、自分の好きなこと、得意なことなど、自己の強みに集中することでした。
そして、足りないリソースは、周りの既に持っている人に依頼し、周囲を最大限に活用したのです。
即ち、自分の持っているもの、特徴から始まり、自分にないものは他者に頼り、最終的にコントロールの出来るものだけに集中し、最終的に最初は想像もしていなかったような結果を得るのです。
エフェクチュエーションの概念は、通常の計画とは異なり、想定範囲のものを創り出すことではないのです。
最初には、想定もしていなかったような理想形を自然な形で創り出す行動哲学のようなものなのです。
これはまさに、人生の達人のレベルを目指すことに他ならないのです。
私はこの概念が大好きになり、更に、学び続けたいと思います。

_上半身のみ_resize-300x283.png)