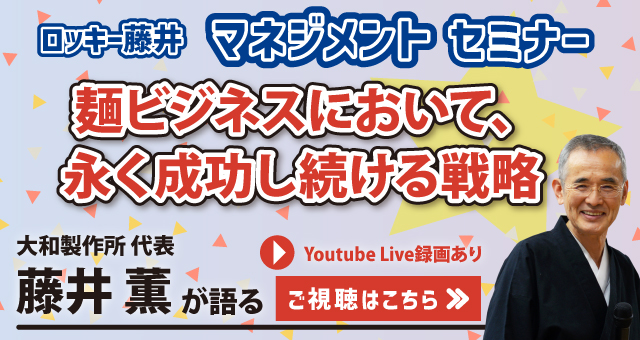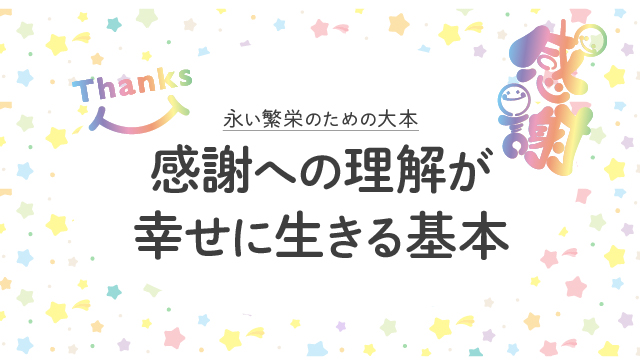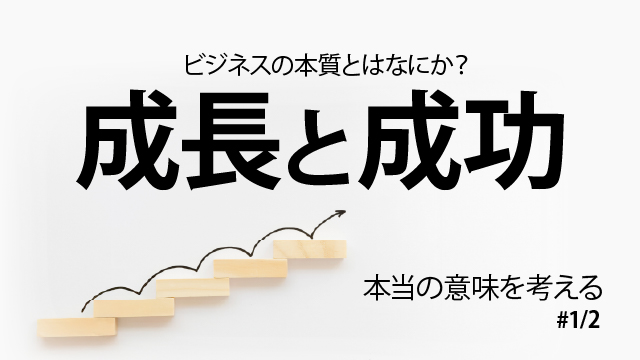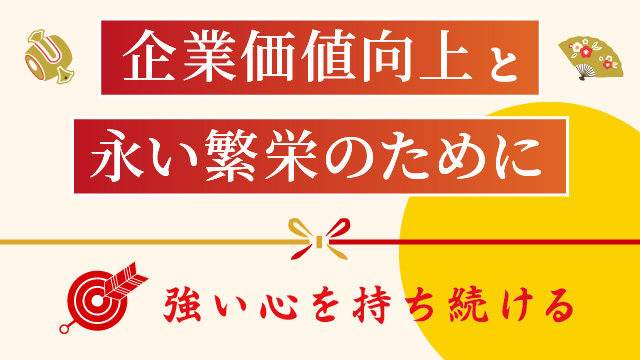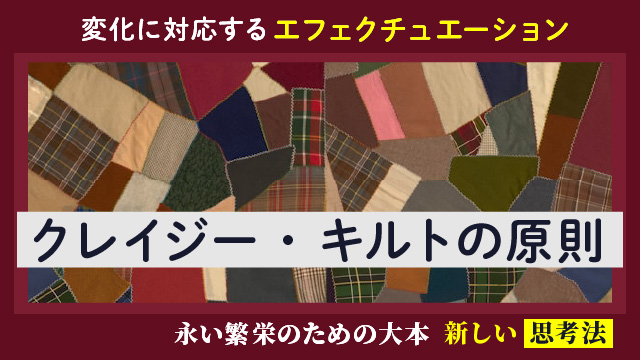
ページコンテンツ
はじめに
今年になってから、皆さんと共有している大変面白い戦略(概念)がエフェクチュエーションです。
私はすっかり、この戦略が大好きになってしまいました。
そして、当社の幹部連中は、この戦略を理解し、使い倒して貰いたいと思っています。
何故、そんなに夢中になっているかと言えば、過去50年前からの事業の中で、私が実体験したことが、そのままトレースが出来ているのです。
今回の「クレイジー・キルトの原則」は、深く思考すればするほど、過去の私の思い出がありありと、目の前に現れます。
長く事業をやっていれば、明日はないな、長くあがいて頑張ってきたが、これがいよいよ最後かと思われるような厳しい状態に何度遭遇したか分かりません。
両手で指折り数えても、全然足りないくらい、たくさんの大変な目に遭遇してきたのです。
実は、昨年の後半でもそのようなことが起きたのです。
それも1回ではなく、何度も継続して起きています。
このクレージー・キルトのような状態を何度も何度も体験しているのです。
私の経験からすれば、そのような場合の最も重要なことは、行動する事であると自信を持っていうことが出来ます。
実に多くの人たちが過去から、何度も何度も私を救ってくれました。
そのような人たちの中の有名な方の中には、上場企業のハチバンラーメンの創業者の故後藤会長、モスバーガーの創業者の故桜田会長もいらっしゃいます。
このような人たちの名前を挙げれば、きりがないくらい多くの人たちに救われたり、良い関係を持つことが出来たりすることにより、今日の当社があるのです。
私の様に、50年の長きにわたり、継続して事業に携わっていると、今回、皆さんと共有しているエフェクチュエーションの概念並びに、クレージー・キルトの原則が、事業において、人生において非常に有効な概念であると分かります。
それでは、そろそろ本文に入っていきます。
アイデアを事業機会へ変換する「行動」の重要性
クレイジーキルト(crazy quilt)の原則
a)熟達した起業家が重視するパートナーシップ
エフェクチュエーションを活用する熟達した起業家の意思決定には、コミットメントを提供できるあらゆるステークホルダーと交渉して、パートナーシップを模索する傾向が見られました。
これは、私の経験からすれば、最高に柔軟性を持った一貫性が要求されると思います。
その代わりに、従来の手法のコーゼーションのようなマーケティングリサーチや競合分析を積極的に行わないという明らかな特徴が見られました。
不可能を可能とするような、ありとあらゆるチャンスを活用して、交渉可能な人たちとは積極的なパートナーシップを求めようとしていたのです。
こうしたエフェクチュエーションを構成する思考様式は、「クレイジーキルト(crazy quilt)の原則」なのです。
b)エフェクチュエーションに基づくパートナーシップの第1の特徴
その場合の交渉相手として、金銭的なものを求めない、自発的な参加者を重視することです。
つまり、なんらかの報酬や強制によって参加するのではなく、パートナーが自ら進んでコミットメントを提供する関係性が大切だと考えるのです。
自発的な参加者を重視するという特徴は、自らコミットメントを提供しようとする相手であれば、そのコミットメントがどのようなものであれパートナーとして歓迎することをも意味します。
つまり、資金や技術など、あなたの事業に必要な資源を提供できる相手をパートナー候補と見なすだけでなく、逆に、そうではない人々も含む自発的な参加者に対して、「何を共創することができるだろうか?」と考えて、積極的に関わろうとするのです。
c)パートナーのコミットメントの形は多様である
自発的な参加者を重視する理由とも関わるのが、パートナーは実際には多様なコミットメントを提供しうる、という第2の特徴になります。
不確実性の高い環境で試行錯誤するエフェクチュエーションのプロセスでは、あるパートナーが果たす役割は1つではなく、実際には、同じ人が複数の異なる種類のコミットメントを提供することも起こります。
事例1)
たとえば、松下幸之助さんが22歳で松下電気器具製作所を起業したことから始まった、現在のパナソニックの歴史のはじまりにも、クレイジーキルト的なパートナーとの関係がありました。
創業間もない松下電気器具製作所は、松下さんが発明した、「改良アタッチメントプラグ(アタチン)」と「2灯用クラスター(二股ソケット)」という2つの製品を家族で製造する、家内制手工業の体制でした。
そこに、2つの製品に目を付けた大阪の吉田商店という大きな問屋がやってきて、総代理店契約を持ち掛けたそうです。
つまり、「うちがその製品を一手に引き受けて広く売り捌いてあげましょう」、という流通のパートナーが自ら名乗りを上げてきたわけです。
それに対して、松下幸之助さんの返答は、申し出を承諾する、あるいは拒絶する、のいずれでもありませんでした。
彼は、大量の製品を販売しようという大手の流通事業者に対して、「あなたがいくら売ってくれてもこと欠かぬように工場設備を拡張したい」と言って、商品供給する前に3、000円の保証金支払いをもとめたのです。
その資金で、松下電気器具製作所は、家内制手工業から、従業員20名を整えて工場生産を開始し、月産5、000個の供給体制を確立するに至りました。
つまり、流通のパートナーであった自発的な参加者が、出資者に変換されたのです。
このように、最初は顧客や取引先という形のパートナーであった人々が、出資者になったり、別の顧客を紹介してくれたり、共同経営者として組織に参画したり、といった別の重要な役割を担うようになることは、スタートアップや新たな事業の立ち上げ時期では決して珍しいことではないでしょう。
d)パートナーは資源だけではなくビジョンをももたらす
当初は起業家自身の手持ちの手段から始まったエフェクチュエーションのプロセスは、新たなパートナーシップが構築されるたびに、「何ができるか」を再定義しながらそのサイクルを繰り返します。
まず、パートナーの参加によって、彼らの手持ちの手段(資源)がプロジェクトに加わるために、手持ちの手段が拡張され、「私は誰か/何を知っているか/誰を知っているか」は、「私たちは誰か/何を知っているか/誰を知っているか」へと変化します。
それに基づいて、「何ができるか」もまた拡張的に再定義されることになります。
一方でパートナーは、新たな資源だけではなく、新たな目的をもたらすことによっても、やはり「何ができるか」の方向性に影響を及ぼすことが想定されます。
パートナーが自発的に参画する背景には、彼ら自身の成し遂げたい思いやビジョン、目的があると考えられるためです。
このようにパートナーは、資源とビジョンの両方を新たにもたらすことで、エフェクチュエーションのプロセス全体の方向性に大きな影響を与え、その未来を起業家と共創していく役割を担うことになります。
キルトづくりに似たエフェクチュエーションのパートナーシップ
クレージー・キルトの原則という奇妙な名称は、下記の図のようなパッチワークキルトより、発想された原則なのです。

さまざまな布(パッチ)を作家がそれぞれデザインする、大きな作品では、それぞれ異なるパッチ、キルト作家と共同制作することで誰も想像していなかった素晴らしい作品が生み出されることがある。
「藁しべ長者」のようなエフェクチュエーションのプロセス
クレージーキルトの原則をわれわれの周りにある事例から、分かり易く説明出来るのが、日本昔話に登場する、有名な昔話の「藁しべ長者」の物語です。
パートナーとの出会いを通じて、新しい資源とビジョンがもたらされることを繰り返し、最終的には思ってもいなかった結末を迎える、というエフェクチュエーションに近い展開は、私たちになじみ深い物語にも見ることができます。
「藁わらしべ長者」の物語は、「今昔物語集」などの古典にも登場する説話で、働けども暮らしが楽にならない1人の貧乏な青年が、篤く信仰している観音様に願をかけたところから始まります。
すると夢のなかに観音様が現れ、「明日お前が初めに触ったものを持って旅に出なさい」というお告げを青年に授けました。
喜んで飛び出した青年は石につまずいて転び、つかんだものは1本の藁しべでした。
それを持って進んでいくと、大きなアブが藁に近寄ってきて離れないので、仕方なくアブを捕まえて藁しべの先に結び付けてさらに歩いていきました。
そこに、牛車に乗ったお金持ちの男の子が通りかかり、アブで動く藁しべを見て、「あのオモチャが欲しい」と一緒にいた母親に泣いてせがみます。
青年は母親の頼みに応じて、藁しべを男の子に譲り、かわりに蜜柑を受け取りました。
さらに歩くと、喉が渇いて行倒れている商人とその付き人がおりました。
蜜柑はただの蜜柑ですが、その時の商人にとってはぜひとも欲しい貴重なものでしたので、青年がそれを差し出すとかわりに上等な反物をお礼に渡してくれました。
その後も、反物が病気で弱った馬と交換され、また介抱して元気になった馬を貸してほしいと大きな屋敷の主人に頼まれ、かわりに留守を預かった屋敷には何年経っても主人が戻らなかったため、
最終的に青年は裕福な暮らしを手に入れることができた、というハッピーエンドの物語です。
起業家の手持ちの資源やアイデアの価値は、その時にどのようなパートナーと出会い、そうしたパートナーが起業家の資源やアイデアにどのような価値を投影するかによって、まったく違った、より大きな価値へと繰り返し変換される可能性に開かれているといえます。
さらに、そのプロセスは偶発性を伴うために、因果論的な目的手段関係では説明できないことです。
新しい価値は、1人だけで実現されることは決してなく、手持ちの手段を携えて新たな行動を起こし、人々と出会い、他者と意味のある関係性を模索することで偶発性を活用しようとする働きかけによって生み出されていました。
事例2)
エフェクチュエーションを活用して大成功した経営者の1人が故ステイーブ・ジョブズで、結果が不確実であっても、むしろ不確実であるからこそ、行動を起こすことが重要であることを主張しています。
1994年にアップル創業者のスティーブ・ジョブズに対して実施されたインタビューです。
「ほとんどの人は受話器を取って電話を掛けようとはしない」と、彼は言っているのです。
シリコンバレー歴史協会が所有する映像のなかに、1994年にアップル創業者のスティーブ・ジョブズに対して実施されたインタビューがあります。
そのなかで、彼は「ほとんどの人は、受話器を取って電話を掛けようとはしない。
そして、それこそが時に、物事を成す人たちと、それを夢見るだけの人たちを分けるものなんだ」と語っています。
実際には、これは彼の中学生時代のエピソードに基づくものです。
12歳当時のジョブズは、機械などのモノづくりに熱中している少年でした。
通っていた中学校でもエレクトロニクス・クラブに所属し、メンバーと一緒に撮影した写真も残っています。
ある時、彼は周波数カウンターという機械をどうしても自分で作りたい、と考えていましたが、それに必要な部品には、一般の中学生が入手できないものがありました。
そこで彼が活用できる「何を知っているか」が2つありました。
1つは、周波数カウンターを製造しているメーカーの1社が、ヒューレット・パッカード社であり、同社には確実に部品があるだろうということでした。
もう1つは、ヒューレット・パッカード社の創業者の1人、ビル・ヒューレット氏は、お金持ちの有名人だったので、自分と同じパロアルト地区に住んでいることを知っていたことでした。
そこで、家にあった電話帳を彼の名前で引くと、1件しか該当する番号がなかったので、そこに電話を掛けました。
たまたま本人が在宅していて受話器を取ったので、自己紹介をして、周波数カウンターの部品を分けていただけませんか、とお願いをしたところ、ヒューレット氏は笑って承諾してくれて、ジョブズ少年は大いに喜んだ、というのが、上記の発言にある「受話器を取って電話を掛ける」という逸話です。
ただし、現実の展開はこれだけでは終わりませんでした。
ジョブズ少年とのやり取りのなかで、彼は本当に周波数カウンターが大好きなのだと感じたヒューレット氏から、今度はもう1つ別の提案がなされました。
それは、ヒューレット・パッカード社の周波数カウンター工場の製造ラインで、夏休みのアルバイトとして働かないか、という問いかけでした。
もちろんジョブズ少年はこれに飛びつき、夢のような夏休みを過ごしたと言います。
さらに、こうして中学生時代に工場の製造ラインのアルバイトとして始まったヒューレット・パッカード社との関係性は、高校生になっても、本社のインターンシップとして継続しました。
そして、スティーブ・ジョブズが高校時代に出入りしていた同社で、当時エンジニアとして働いていたのが、スティーブ・ウォズニアックだったのです。
われわれの多くが知っているように、2人は意気投合し、後に共同でアップル・コンピュータを立ち上げます。
つまり、彼が先のインタビューのなかで語っているのは、こういうことでしょう。
多くの人は「部品を分けてください」という電話を掛けるという行為は、たわいもないことだと感じたり、あるいは厚かましいことだと感じたりといったさまざまな理由から、実際に実行に移す人は少ないかもしれません。
しかし、あの時ジョブズ少年が電話をかけなければ、おそらくアップルという会社は存在しなかっただろう、と考えられるのです。
未来は不確実で予測できないため、当初思い描いていた通りには進まないことが多い一方で、何気ないパートナーとの相互作用が、想像もしなかった展開へとつながる可能性もまた、未来が不確実であるからこそ十分にあると考えることができるのです。
未来は不確実で予測できないため、当初思い描いていた通りには進まないことが多い一方で、何気ないパートナーとの相互作用が、 想像もしなかった展開へとつながる可能性もまた、未来が不確実であるからこそ十分にあると考えることができるのです。
パートナー獲得のための行動:問いかけ(asking)
パートナーに対する2つのアプローチ
① パートナーのコミットメントを獲得する行動
エフェクチュエーションにおいて、コミットメントを得るためのパートナー候補への働きかけは、「ask」や「asking」と呼ばれます。
これは何かを求めて尋ねることを指しますが、日本語では「問いかけ」と訳すことができると考えています。
・コーゼーションの発想⇒「売り込み(selling)」が重視
・エフェクチュエーション⇒「問いかけ(asking)」が重視
②「売り込み(selling)」と「問いかけ(asking)」という2つのアプローチの違い
a)コーゼーションに基づく「売り込み(selling)」
コーゼーションの場合には、分析や予測に基づいて最適なアプローチを追求する発想であるため、事業アイデアもよく練られた最善のものが求められるでしょう。
そこでパートナー候補に対して協力を求める際にも、それがいかに優れているのかを積極的に説明することで事業アイデアやビジョンを売り込むこと(selling)が重視されがちです。
つまり、コミットメントを獲得しようとする行動の結果は、成功か失敗のいずれかであり、基本的には一人のパートナー候補に対して一回きりの交渉が想定されています。
b)エフェクチュエーションに基づく「問いかけ(asking)」
アイデアは起業家自身の「手持ちの手段(資源)」と許容可能な損失」に基づいて生み出された「何ができるか」であり、また後に繰り返し再定義される可能性に開かれた、暫定的なものにすぎません。
そして起業家のパートナー候補に対するアプローチでは、どのような形であれば相手とともに未来を創っていくことができるか、をオープンに問いかける(asking)ことが重視されます。
そして、こうした多様な形の望ましいパートナーシップを模索するためには、起業家が自らのアイデアを積極的に説明すること以上に、相手の話をより多く聞くことが、極めて重要になります。
どのような資源の提供であれば、相手が許容可能なのか、思いやビジョンを含む、どのような手持ちの手段(資源)を相手は持っているのか、といった点について理解できて初めて、お互いにとって意味ある取り組みを共創できるといえるでしょう。
事例3)クラウドソーシングサービスを提供する株式会社クラウドワークスCEOの吉田浩一郎さん
出資を断られたことで11億円を調達する
起業家の問いかけ(asking)について、具体的な事例を通じて理解を深めたいと思います。
クラウドソーシングサービスを提供する株式会社クラウドワークスCEOの吉田浩一郎さんは、2011年に同社を創業後、翌年には3億円の増資に成功し、事業は順調に成長していたものの、吉田さん自身はいっそう成長スピードを上げる必要を感じていました。
ただ、どうすればよいかの打ち手がわからず、出かけた書店で出会ったのが、ライフネット生命を創業した岩瀬大輔さんが出版された『132億円集めたビジネスプラン』という本でした。
その本のなかで、132億円を集めた投資家の谷家衛さんの名前を知った吉田さんは、自身の「誰を知っているか」のなかで谷家さんを知る方に頼み込み、面会の機会を取り付けます。
会ってすぐに、クラウドワークスの事業を説明し、「私も132億円集めたいんです」と率直に伝えました。
しかし、30分ほどできっぱり断られてしまいます。
「東大・ハーバード大学のビジネススクール出身で、金融とコンサルの世界で生きてきた岩瀬さんとは違うのだから、目指す相手が違う」と 言われて、吉田さんは傷ついたそうですが、そこで落ち込んで退散しただけならば、単なる失敗に終わったでしょう。
しかし、吉田さんは谷家さんに、もう1つ別の問いかけを行いました。
それは、「じゃあ私は誰を目指せばいいんですか?」という質問でした。
多くの優れたベンチャー経営者を知っている谷家さんにとってはおそらく返答可能な、しかし、初対面の吉田さんに答える義理は必ずしもない質問でした。それでも谷家さんは少し考えた後に、「サイバーエージェントの藤田さんがいいんじゃないかな?人間力で組織を率いるタイプの経営者を目指したほうがいいよ」と言ってくれました。
吉田さんは感謝を述べ、今度はまた人づてに頼み込んで、サイバーエージェントの創業経営者である藤田晋さんと面会を取り付け、事業に関するまったく同じ説明をしました。
すると今度は、30分もたたないうちにサイバーエージェントのファンドから10億円の出資が決まり、そこに外部の資金が加わって、合計11億円の調達が実現したのでした。
その後、吉田さんは藤田さんのアドバイスに従い、クラウドワークスは2014年12月に東証マザーズへの上場も果たすことになります。
パートナーもまた「手中の鳥」と「許容可能な損失」の範囲で コミットする
吉田さんの谷家さんへの問いかけの例でも見ることができるように、エフェクチュエーションを活用する起業家は、当初期待したものとは違っていたとしても、相手と交渉をして何らかのコミットメントの獲得を模索しようとします。
谷家さんは当初の吉田さんが期待したような直接の出資者にはならなかったものの、サイバーエージェントの藤田さんの情報を提供してくれたことによって、クラウドワークスが増資を獲得するプロセスにおける重要なパートナーであったといえるでしょう。
この事例から学ぶことのできるもう1つの重要な点は、高い不確実性を伴う取り組みを行う起業家が、まずは手持ちの手段(資源)と許容可能な損失の範囲で行動するのと同じように、問いかけられたパートナー候補もまた、手持ちの資源と許容可能な損失の範囲でコミットメントを行う、ということです。
その点について理解を深めるために、クラウドワークスの創業時に吉田さんが行った、もう1つの問いかけの事例を見てみましょう。
同社が事業とする「クラウドソーシング」とは、インターネットを使って不特定多数の個人に仕事を発注することができる仕組みであり、仕事を発注したい側(主に企業)と、受注したい側(主にエンジニアやデザイナー等のフリーランスの個人)との間を取り持つマッチングサイト「クラウドワークス」によって、その仕組みを提供しています。
これは一般に、ツーサイド・プラットフォーム(two-sided platform)と呼ばれるプラットフォーム・ビジネスであり、発注側にとっては優れたエンジニアやデザイナーが多く登録しているサイトほど魅力的であるため、より多くの発注を行うことが期待されますし、受注側にとってはよい仕事を発注してくれる企業が多いサイトほど魅力的であるため、より多くの優れたエンジニアやデザイナーが登録することが期待されます。
つまり、取引を行う両サイドの利用登録者が増えていけばサービスの価値も高まる「ネットワークの外部性」によって、好循環が生まれますが、逆に、サービスの立ち上げ時点では、発注側と受注側の両方が不在の状態からどうやって集めるのかに困難が伴います。
吉田さんはもともと法人営業が得意な方でしたが、最初に集めたのは仕事を受注してくれるフリーランスの側でした。
そのために吉田さんは、世の中でエンジニアやデザイナーとして活躍している著名な方々をリストアップして、その1人ひとりに対して問いかけを行いました。
そうした人々のなかには、プログラム言語Rubyで有名なエンジニアやiPhoneアプリ開発で名人として知られる人物、天才ハッカーとして名を馳せている学生をはじめ、上場企業のエンジニアや外資系クリエイティブ企業のデザイナーも含まれていましたが、彼らに対して「クラウドワークスに登録をしてもらえませんか」と問いかけたわけではありません。
そのような依頼であれば、多忙な彼らにとって許容可能な損失を超えるものとして、受け入れ難いものだった可能性も高いでしょう。
そのかわりに、吉田さんが著名なエンジニア・デザイナーに対して行ったのは、「エンジニアがフリーランスとして仕事ができる未来の働き方を、一緒に作ってもらえませんか」という問いかけでした。
具体的には、SNSで直接彼らにアプローチをして、クラウドワークスの事業の趣旨を伝え、もし賛同していただけるならば彼らの写真をサービス提供サイトのトップページに掲載させてもらえないか、と問いかけたのです。
その結果、多くの著名なエンジニアやデザイナーの写真がクラウドワークスのサイトのトップページに掲載されることになり、それを見て事前登録をするプロフェッショナルのエンジニア、デザイナーの数は、サービス開始前の2012年2月時点で1、300名以上に上りました。
そして吉田さんは、「これだけのプロが集まっている」というリストを携えて企業を回り、仕事を発注する企業約30社を集め、同年3月、クラウドワークスのサービスが開始されたのです。
相手が経済的な見返りを求めているとは限らない
パートナー候補として他者に問いかけを行う際に、相手に対して何も見返りを提供できない、と考えて躊躇する人もいるかもしれません。
しかし、相手が期待したコミットメントを提供してくれるのか、それがどのような理由によるものなのかは、結局のところ相手が判断する問題であるといえます。
また、先のクラウドワークスのサービス立ち上げ時の逸話に見られるように、協力をしてくれる相手が、必ずしも直接的なリターンや経済的な見返りを期待しているとは限らない場合も多いのではないかと考えられます。
たとえば、起業家一人では実現できないような価値ある未来を自分が参画することで現実にできると考えるとき、自分では十分に認識していなかった自らの手持ちの手段の価値を起業家が評価してくれるとき、あるいは、起業家のビジョンに共感して単純にワクワクした気持ちを感じるとき、問いかけを受けたパートナーにとって、もしコミットメントが許容可能な損失の範囲にとどまるのであれば、見返りがなくとも協力をする理由は十分にあるのではないでしょうか。
社会心理学の実験結果からは、私たちが見知らぬ人に対して何かを頼むとき、
他人が直接の助けの要求に応じる可能性を過小評価する傾向があることが明らかにされています。
具体的には、アンケートに協力を依頼する、携帯電話を貸してもらう、キャンパス内の体育館まで案内してもらう、といった突然の依頼に対して、実際に依頼をした実験参加者の学生たちは、その成功確率を約50%も低く見積もっていたのです。
直接誰かに助けを求める場合、意外に協力が得られやすい理由は、それを断ること(援助をしないこと)の社会的コストのほうが実際には大きいためとも解釈されていますが、同時に、難なくできる行動であれば、助けに応じる側がそれによって満足や自尊心の向上といった心理学的なメリットを得られやすいためであることも指摘されています。
③相手が経済的な見返りを求めているとは限らない
パートナー候補として他者に問いかけを行う際に、相手に対して何も見返りを提供できない、と考えて躊躇する人もいるかもしれません。
しかし、相手が期待したコミットメントを提供してくれるのか、それがどのような理由によるものなのかは、結局のところ相手が判断する問題であるといえます。
④起業家的熟達の基礎としての「問いかけ(asking)」
問いかけ(asking)の重要性は、学会での議論を通じて明確化されてきた経緯があります。
そのきっかけとなったのは、2009年に学術雑誌『ジャーナル・オブ・ビジネス・ベンチャリング(Journal of Business Venturing)』に掲載されたロバート・バロンによる論文でした。
サラスバシーらの研究グループは、同雑誌に掲載された別の論文で「熟達した起業家は意思決定の際に不確実性への対応に熟達するうえで最重要の活動こそが「the Ask」、つまりは「問いかけ(asking)」である、と結論づけたのです。
なぜならば、資源獲得の成功/失敗に焦点を合わせる売り込み(selling)とは異なり、問いかけ(asking)によって、他者の多様なコミットメントを獲得できれば、事前の予測が不可能な状況下でも、取り組みの実効性をパートナーとともに高めて実際に優れた起業家的成果に結びつけられると考えられるためです。
また、新しいビジネスを立ち上げるために、「誰に」「何を」問いかけるかは状況によってさまざまですが、「どのように」問いかけるかについては継続的な実践と改善が可能です。
すなわち共創的な関係を構築する問いかけ(co-creative ask)へと変化し、パフォーマンスを高めることにつながると主張されました。
実際に、問いかけ(asking)には、熟達に必要な意図的な練習の基礎となる、「目的を持った練習(purposeful practice)」の6つの必須要件を満たしていることも確認されました。
Ericsson (2018) によればそれは、
- 活動が、目標とするパフォーマンスに有意味に関連したタスクに分解または変換されていること
- 活動を繰り返し練習することができること
- 練習はパフォーマンスを向上させるという大きな目的によって動機づけられていること
- パフォーマンスに関するフィードバックが利用可能であること
- 練習の活動はパフォーマーの現在のスキルレベルを考慮したものでなければならないこと
- 活動は熟達の蓄積に関連した「最近接発達領域」(Vygotsky 1978)内のものでなければならないこと
です。意図的な学習には、これらに加えて、
7. 練習は目標とするパフォーマンスを達成するために他の人をうまく訓練したことのある教師によって監督され、設計されていること
が要件として追加されます。
つまり、パートナー獲得のために他者に問いかける行動は、うまくいったかどうかの結果のフィードバックを得ながら、繰り返し練習可能であり、また学習や支援を得ながら工夫することで、すぐにはできないことも1人でできるようになっていく、という意味で、目的を持った練習に当てはまっているのです。
問いかけ(asking)は、意識せずとも日頃から実践しているという人もいるでしょう。
一方で、誰かに何かを頼むこと自体に苦手意識を感じる、最初はうまくできない、と感じる人も多いでしょう。
しかし、それこそがエフェクチュエーションの活用、起業家的な熟達にとって最も重要な、上達可能な要素であるため、自分にとって許容可能な損失の範囲で、ぜひ繰り返し練習をしていただければと思います。
さいごに
今週のクレージー・キルトの原則はいかがだったでしょうか。
これからの不確実な事象が起き続けるビジネスの世界の中で、永く強く生き残り続ける非常に効果的な概念であり、考え方の素晴らしい実践手法だと思います。
最期まで読んで頂いた読者の皆様に感謝するとともに、ぜひ、皆さまにとって当社がクレージー・キルトのパートナーの一員として、皆さまのビジネスに最大の価値をもたらすパートナーとして、貢献出来ることを期待しております。
ぜひ、当社の持つ様々な資産を活用し、素晴らしい成功を勝ち取ることをお祈りします。
今年もシッカリ、当社を活用して下さい。
引き続き、皆さまには有益な情報をお届け致します。

_上半身のみ_resize-300x283.png)