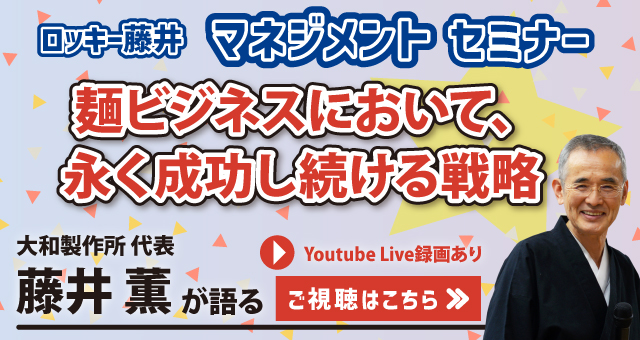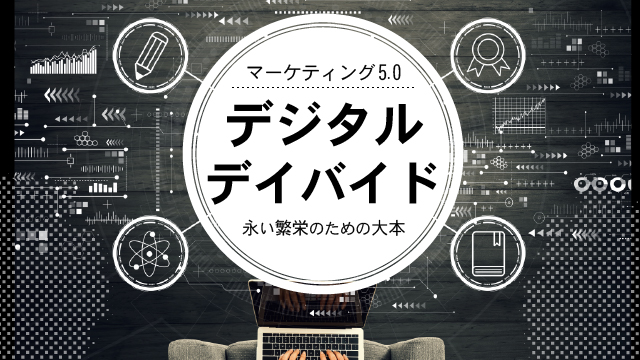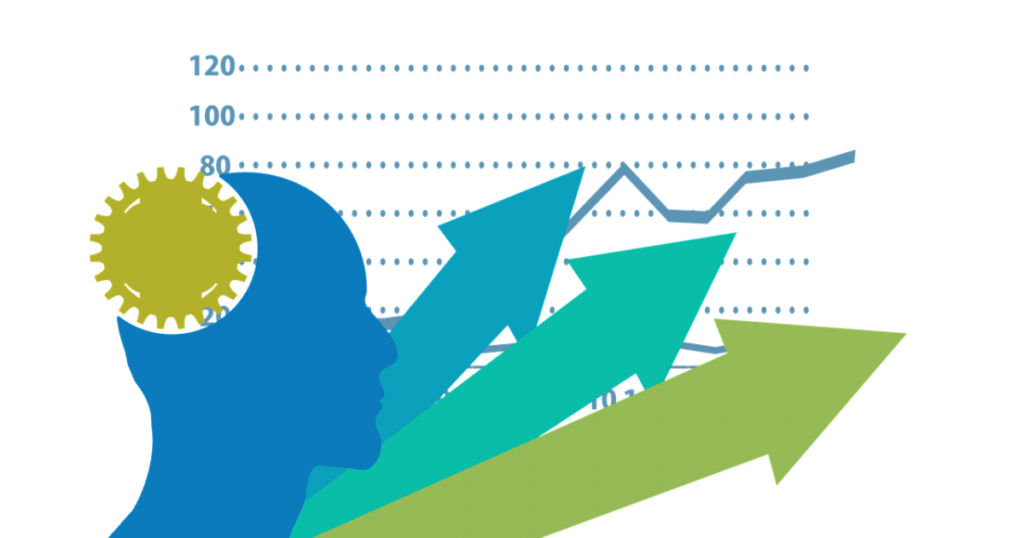ページコンテンツ
はじめに
5年前に発生したコロナのように、この世で生きている限り、或いは日本国内で生活している限り、昨年元旦に発生した能登半島沖地震のような予測出来ない不確実性は、いつ何時発生するかは予測することが難しいのです。
そのような現実の中で、永く強く生き残るための実践的な手段として、予測して対処するのではなく、起きたことに対処するエフェクチュエーション(不確実性の高い状況で意思決定を下すための思考様式)の概念を学んでいます。
先週のテーマは、永い繁栄のために何か新しいことに取り掛からなければいけない場合、「許容可能な損失の原則」により、どこまでの損失までであれば実行するかを、最初に決めてから始めるということでした。
そうすれば、うまくいかなかった場合でも、致命傷になるような傷は発生しないのです。
今週のテーマは、「レモネードの原則」では、食べられないような酸っぱいレモンが手に入っても、それを無駄にしないで、有効活用して美味しいレモネード作りの原料として活用し、価値を生み出す商品に作り変える考え方です。
これを深く考えてみれば、どの様なこと、普通考えれば不利になるようなことが起きても、起きたことの本質を理解し、その性質を活用して、新しい価値あるものを作り上げることなのです。
例えば、5年前にコロナが突然発生し、交通機関、飲食業、ホテル、旅館業などは大変大きな痛手を受けました。
そのような中で、コロナをビジネスにネタにして、この時期に大成功したビジネスを挙げると、新型コロナ検査キットをいち早く開発し、製造したメーカーとか、コロナのワクチン開発業者、飲食ビジネスでは、宅配ビジネスを推進したウーバーイーツ、そしてそれに乗って宅配を始めた多くの飲食店も挙げられます。
コロナの検査薬とか、ワクチンは非常に難易度が高いので、誰でも出来るようなビジネスではないのですが、宅配ビジネスを始めることは、誰でも簡単に取り組むことが出来ました。
次に、エフェクチュエーションの対極のコーゼーションの違いです。
不確実性の削減を重視するコーゼーション
コーゼーション(因果論)の発想に基づくこれまでの経営学では、こうした不確実性への対処に共通する基本的方針として、「追加的な情報を収集・分析することによって、不確実性を削減させる」ことが目指されてきたことはすでに確認しました。
さまざまな方法によってできる限り綿密に環境を分析し、結果の不確実性を削減したうえで、最適な計画を立てることを重視するのです。
偶発性の活用を重視するエフェクチュエーション
コーゼーションの対極にあるエフェクチュエーションでは、予期せぬ事態は不可避的に起こると考え、むしろ起こってしまったそのような事態を前向きに、テコとして活用しようとするのです。
こうした熟達した起業家の思考様式は、「レモネード(lemonade)の原則」と呼ばれます。
美味しい果物を手に入れたいと期待したにもかかわらず、酸っぱくて食べられないレモンしか手に入らないのなら、それは不都合な結果といえますが、だからといって手にしたレモンを捨てたりせずに、酸っぱいレモンはより美味しい飲み物を作る原料にすればよいという発想です。
3種類の不確実性
エフェクチュエーションの概念を提唱したサラスバシーは、私たちが不確実性と呼んでいるものに、3つの異なるタイプがあることを、3種類の壺の例によって説明しています
ビジネスが成功するかどうかという不確実性の問題は、この例ではもっと単純なゲーム(中身の見えない壷の中に手を入れて、赤いボールを引き当てたら勝ちで、賞金が獲得できる、というゲーム)の成功にたとえられます。
①第一の壷
壷の中に赤いボールが50個、緑のボールが50個入っています。
⇒赤いボールを引き当てられるかどうかは不確実であるものの、成功確率が50%であることは明白です。
②第二の壷
壷の中に赤いボールと緑のボールが、それぞれ何個ずつ入っているかも事前にはわかりません。
⇒結果が成功するかどうかの不確実性に加えて、成功確率も不確実であるといえます。
⇒ただし、ゲームにチャレンジをする前に試しに何度か引いてみることができれば、だいたい10回に2回程度赤いボールが出ることを学習することができるでしょう。
つまり、追加的な情報を収集することによって、成功確率が約20%であると予測できるようになるのです。
③第三の壷
事前に壷の中の赤いボールの数はわかりません。
⇒さらに第二の壷と同様に、試しにボールを引いてみることで成功確率を予測しようとしたところで、何度引いても一向に赤いボールが出てきません。
⇒そればかりか、緑のボールすら出ず、青いボールや黄色いボールなど、
想定しなかった色のボールばかりが出てきます。
こうした状況では、赤いボールが本当に入っているのかどうかさえ疑わしく、成功確率も知りようがありません。
予測によっては対処できない不確実性が存在する
①第一の壷
成功確率が自明な事象というのは、現実のビジネスにおいてはありえないでしょう。
②第二の壷
確率を予測した結果、赤いボールが出る確率は20%と決して高くないことがわかった場合にも、失敗するリスクの大きさが明らかであるため、それに対して保険をかけるといった方法で、予測に基づいて不確実性に対処することが可能です。
③第三の壷
このことから、この第三の壷のように、計測不可能な真の不確実性は、「ナイトの不確実性(Knightian Uncertainty)」とも呼ばれます。
つまり、多くのビジネスで想定される不確実性(リスク)に対しては、コーゼーションの予測合理的なアプローチによって対処することが有効である一方で、起業家が生み出す新たな事業や市場といったものは本質的にユニークであり、同類の経験を多く集めて分析することによって不確実性を縮減することはできないのです。
予期せぬ事態を「手持ちの手段(資源)」として活用する
起業家は、予測不可能なナイトの不確実性のなかでも、むしろ予期せぬ事態そのものを自らの手持ちの手段(資源)として取り込んで活用することで、実行可能な新たな行動を定義し、結果として実際に賞金を獲得できる可能性を高めることができるのです。
偶然がきっかけとなって生み出された科学的発見
こうした予期せぬ事態の発生とその活用の事例がしばしば登場します。
- 事例1)イギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミング
- 事例2)2002年にノーベル化学賞を受賞した島津製作所の田中耕一さん
いずれの事例でも、意図された行動の結果からではなく、思ってもいなかった事態をきっかけとして、重大な科学的発見が生み出されていることがわかります。
失敗から生まれた世界的なヒット製品
このように予期せぬ事態をきっかけに成功が生み出された事例は、ビジネスの分野でもいくつも見ることができます。
企業の製品・技術開発においても、当初は〝失敗〟と呼べるような予期せぬ結果が、その後に異なる形で活用されることで、より大きなイノベーションにつながることもあります。
- 事例1)3Mが発売する「ポストイット(Post-it)」
- 事例2)「手振れ補正技術」として知られる振動ジャイロセンサーの技術
まとめ
今回の私のブログをここまで読み込んでくれた皆さんであれば、「レモネードの原則」を実際のビジネスに活用しようとした場合に、最も必要とされる要素とは、自分はどんなことがあっても成功すると信じることが出来る底抜けの楽天主義、絶対に諦めないで、行動することを止めない意志力は欠かせない要素であることは良く理解出来たはずです。
エフェクチュエーションは従来の因果論をベースにしてコーゼーション(目標から逆算して達成のための手段を考える意思決定手法)とは全く異なる積極果敢な行動をベースにした実践論でもあるのです。
そして、既に自分が持っているさまざまな価値を活用して、起きたことの特質も活用し、結果として、自分に有利な価値ある状況を作り上げる実践なのです。
また、日々の経営に真剣に取り組んでいると、順境よりも逆境に遭遇することが多いのです。
そして、背伸びすればするほど、打たれるのです。
過去の私はそのような逆境に遭遇した場合は、厳しいなとか、ついてないと思ったりしたことがありました。
ところが、5年前のコロナ発生時は、今までの世界は2度と戻らないと思い、コロナが起きたことを活用して、新しい取り組みを始めたのです。
これは結果として、当社にとって非常に良い結果をもたらせてくれたのです。
更に、現在も日々、さまざまな事象に遭遇していますが、一見、厳しい事象が起きても、それを社員一丸となり、乗り越えるための材料とすることにより、強い会社作りの原点になるように感じるようになりました。
従って、下記の①~⑤の視点を持って、予期せぬ事象に対処することの大切さを感じます。
どの様なことが起きようと、起きることが一見良いことであれ、不利なことであってもそれらを積極的に活用することに最終的に実りある結果に結び付けるのです。
①予期せぬ事態に気づく
1つの予期せぬ事態が起こった時に、それが幸運な偶然なのか、そうでないのかは、その時点ではわからないことがあります。
一見してネガティブな事態も、それを活用する行動を伴うことで初めて、大きな成功につながる「幸運な偶然」に変換されるのです。
②同じ現実に対する見方を変える(リフレーミング)
見方の転換は、「リフレーミング」とも呼ばれます。
リフレーミングは、もともと心理療法で活用されてきた言葉であり、自身の認知や活動の枠組み(フレーム)が変わることによって、同じ出来事に対する受け止め方や反応の仕方が新しいものに変わることを意味します。
熟達した起業家は、同じ偶然の出来事に対してその捉え方を意図的に変えることで、積極的に可能性や機会を見出そうとするのです。
③予期せぬ事態をきっかけに「手持ちの手段(資源)」を拡張する
あらゆる予期せぬ事態は、手持ちの手段(資源)の拡張機会として捉えることが可能です。
手持ちの手段(資源)は、「私は誰か」・「何を知っているか」・「誰を知っているか」という3つの要素を特徴としますが、予期せぬ事態は、手持ちの手段(資源)に新たな要素を付け加える機会であるのと同時に、すでに手にしている自身の「手中の鳥」に気づく機会にもなりえます。
④拡張した手持ちの手段(資源)を活用して新たに「何ができるか」を発想する
こうして、手持ちの手段(資源)が拡張的に変化したならば、エフェクチュエーションのサイクルに従い、それらの手段を用いて「何ができるか」をもう一度問い、新たな行動につなげることが重要です。
そのために極めて重要なのは、あなた自身がその取り組みを意義あるものと考え、自分で決めて行動しているという前提です。
それが自らにとって重要な取り組みであればこそ、たとえ想定外の失敗を含む不測の出来事が起こった場合にも、それすらを資源として活用することができるのです。
⑤レモネードの原則は「許容可能な損失の原則」を補完する
「レモネードの原則」は、それでも想定しきれない不確実性を含む予期せぬ結果を、むしろ自らの手中の鳥を拡張する機会(「手中の鳥の原則」)と捉え、より美味しいレモネードの材料にするためにテコとして活用することで、こうした「許容可能な損失の原則」を補完する形で機能します。
私たちは、理想的な手持ちの手段から始めることも、未来を完全に見通すこともできないかもしれませんが、偶然に与えられたものを活用することで、意味のある新しい行動を創り出すことはできるのです。
今週のレモネードの原則はいかがだったでしょうか。
これからの不確実な事象が起き続けるビジネスの世界の中で、永く強く生き残り続ける非常に効果的な概念であり、考え方の素晴らしい実践手法だと思います。
皆さんもレモネードの原則を活用して、素晴らしい成功を勝ち取ることをお祈りします。
今年もシッカリ、当社を活用して下さい。
引き続き、皆さまには有益な情報をお届け致します。

_上半身のみ_resize-300x283.png)