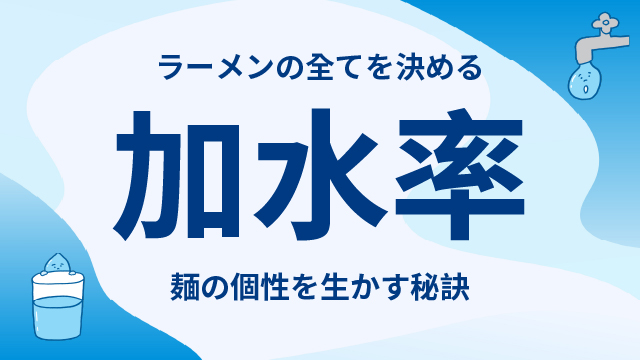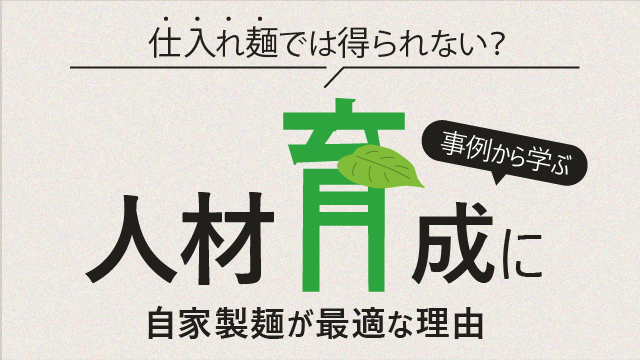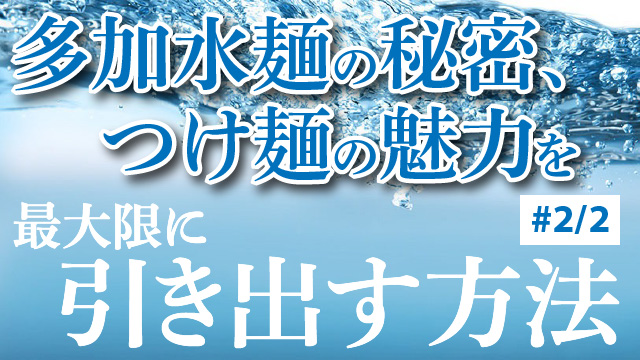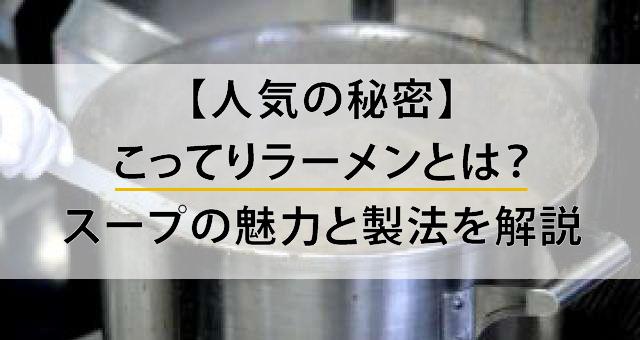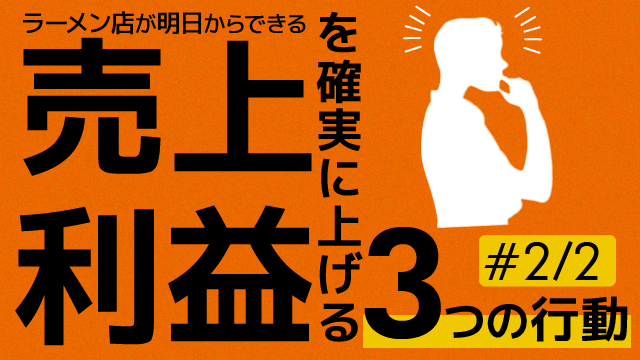ページコンテンツ
はじめに
この記事ではラーメンを「材料、形状、加水率」の観点から分類し、それぞれの違いを分かりやすく解説します。
ラーメンの種類を体系的に理解することで、ラーメンの知識を深め、自分なりの分析や考え方を身に付けることができます。
「ラーメン」について一緒に学んでいきましょう。
この記事では、ラーメンの材料、形状、加水率別に、ラーメンごとの特徴を分類ごとに解説しています。
分類をしていくことで、知識を体系的に整理できます。
さらには、分析する考えや、ラーメンに対する一貫した見方を、築くのに役に立ちます。
これから「ラーメン」について一緒に学んでいきましょう。
1. ラーメンの具材による分類
ラーメンとは何か?
当たり前の答えかもしれませんが、ラーメンは麺類の一種です。
古代中国で生まれたもので、小麦粉の生地を手で伸ばし、割って、また伸ばして、生地の塊が多数の麺線に分かれます。
その後、茹でて箸で食べられるようにした小麦粉の加工品のことが麺です。
ラーメン(拉麺)を表す「拉」の字は、まさに「伸ばす」「引っ張る」を意味する言葉です。現代のラーメンの製麺方法は、必ずしも当時の製法を忠実に再現しているわけではありませんが、ロール式製麺機は、グルテン構造の形成と保持を図ることで、初期のラーメンの製造技術の精神を継承しています。
1.ラーメン作りには、欠かせないかん水

ラーメンの特徴として、「かん水」と呼ばれるアルカリ性化合物を使用することが挙げられます。昔も今も変わらず使用されています。
まず「かん水」とは、中国語で「灰汁」を意味する「建水」の日本語読みです。かん水は、ラーメンに辛味を与えるだけでなく、他の重要な役割も担っています。
ラーメンを分類しようとするとき、厳密には「かん水」こそが、ポイントになってきます。
日本の食品工業規格では、ラーメンは「中華麺」という分類に属します。
定義上は「かん水」が入ってなければなりません。これが最初の分類する基準です。
日本で使われている「かん水」は、
・炭酸ナトリウム(Na2CO3)
・炭酸カリウム(K2CO3)
上記の粉末の組み合わせです。
粉末は、市販されているのが普通です。
2. 小麦粉を使用する/しないラーメン
ラーメンは、中国で誕生して以来、小麦粉を主材料とした料理が主流でした。
近年では、ラーメンの普及にともない、小麦粉を使わないラーメンも登場しています。
栄養学的に、小麦を控えるという食事法の登場やアレルギーなどの体質的な問題もあるからです。
その結果、小麦を食べることができない人たちに合わせたグルテンフリーのラーメンが開発されています。
小麦粉入りのラーメン


通常、ラーメンは小麦粉、かん水、水などを混ぜて製麺された麺を使います。
多くのお店では、このタイプのラーメンが出されていて、思い浮かべるのは、たいていこの黄色い麺のことではないでしょうか?
グルテンフリーのラーメン


上記の写真がグルテンフリーのラーメンです。
近年開発が進んでおり、小麦粉の代わりに、米が用いられることもあります。
米を主材料とした麺は、米粉麺(こめこめん)とも呼ばれています。
そのほか、日本の十割蕎麦も、グルテンフリーの分類として挙げられます。
3.卵を使うか、使わないか?卵のあり/なし
ラーメンに、卵が入っているのが、当たり前だと思っている人がいます。
しかし、なかには、入っていないラーメンも存在します。
なぜなら、ラーメンの製法やレシピで作り方が異なるからです。当然、卵入り/なしで、ラーメンの見た目や味、スープとの相性も異なります。
また、卵でも全卵かどうかでも変わってきます。
卵入りラーメン

卵なしラーメン

4.さまざまな色合いのラーメン
ラーメンに香りや味、色をつけるために、主に植物由来の原料を微粉末にし、添加物として使用することもできます。
添加する原料によっては、通常の製法以外に、柔軟に変化させる必要がでてきます。
麺を試作してみて、うまく製麺できない場合は、個別で麺の試作相談も可能です。

5.グルテンを通常より配合
細い麺、とくに、博多とんこつラーメンに代表される「バリカタ」に使用される麺には、グルテンが添加されやすいという特徴があります。
なぜなら、麺の硬度を高めるためです。
具体的には、製麺中に小麦粉混合物に、分離されたグルテン粉末を加えることで実現できます。
麺の見た目は変わりませんが、食感に影響を与えます。

6. 低灰分のラーメン
灰分は、ラーメンの見た目や茹で上がり、さらには、ラーメンスープに入れた時の、麺の状態を左右する重要な材料です。
しかし、最近の食品・栄養事情に詳しい方ならご存知かと思いますが、ひと昔の常識や医学的なアドバイスからすると、精製すればするほど健康に良いというわけでは、なくなってきています。
そこで全粒粉ラーメンの登場です。
低灰分ラーメン


全粒粉ラーメン


7. 塩の有無
一般的なレシピでは、ラーメンには、少量の塩が欠かせません。
理論的には、使わない方法もありますが、あまり一般的ではありません。

2. ラーメンの形状による分類
麺の切り方によっても、さまざまな種類があります。主に、ロール式製麺機で製麺されますが。カッターに取り付ける切り刃と呼ばれるパーツを交換することで、さまざまな麺に仕上げることが可能になります。
手もみ麺など、切り出し後の麺線を加工して麺の形状を変えることもあります。
スープの相性や食感によりますが、ここはお店ごとの、こだわりが出るポイントです。
1. 角切り麺
角切りは、ラーメンで使用される代表的な切り方です。
カッターを通過する、麺生地の幅とカッターの溝の幅が同じであれば、四角い麺になります。
角切りラーメン


2.丸い麺
丸いタイプの麺もよく見る形です。
丸い麺といえば、押し出し式の製麺機が一般的です。
ロール式ラーメン製麺機で作る場合は、丸い溝を持つ専用カッターを取り付けることで、簡単に丸い形のラーメンを作ることができます。
ロール式製麺機の麺線は、鍛えられた生地をカッターで切っているため、押し出し式と比べ、品質が良いとされています。
丸切りラーメン


3. 平打ち麺
こちらも、一部ラーメン店で使われることがある麺の切り方です。
薄い生地を広い溝の付いたカッターに通すと、パスタや、きしめんのような、平たい麺になります。
平打ちラーメン

4. 逆切り麺
平打ちタイプとは、異なり麺生地の厚みがカッターの溝幅より大きい場合「逆平打ち」タイプの長方形の麺になります。
このタイプのラーメンは、カッター面の「ザラザラ感」が強いため、ラーメンを食べる時、箸で持ち上げたときにスープがよく絡むという特徴があります。

5. ストレート麺
まっすぐな麺のことです。
切り刃から切断された麺線をそのまま玉取りすると、このようなストレートの麺になります。

6. カーブ、カールする手もみ風
切り刃(カッター)に特殊な付属品を取り付け、麺を絞り出すようにしたり、麺を手で押しつぶしたりして、麺に圧力をかけると、波打つような形状になります。
ストレート麺から職人が手作業で、手もみすることで、手もみ麺ができあがりますが、カット時の工夫で、簡単に手もみ風の麺を作りだすこともできます。

3. ラーメンの加水率による分類
麺には、「小加水麺」「中加水麺」「多加水麺」の3種類に分類されます。
・麺の水分量(水和度)
・大きさ(太さ・幅)
これらには、相関関係があります。
乾燥した麺は細く、水分量が多い麺は、幅が広い傾向があります。
少加水ラーメン麺 (加水率:~30%)
加水量が小麦粉に対して、30%以下の麺のことを、小加水麺として一般的に分類されます。
小加水麺は、細い麺で製麺されることが多く、ロール式製麺機で麺生地を圧縮し、固めることで、繋がりのある麺生地を、作り出します。
水分量が少ないため、小加水の麺を手作業で作ることはかなり難しく、加水量が少なくなるほど、手打ちは不可能に近づきます。

中加水ラーメン(30~39%)
加水量が、小麦粉に対して30%~39%あたりの麺は、「中加水麺」として分類します。
中加水の麺は、スタンダードな中華そばのような麺で、細め~太めまで、対応範囲が広いです。
水分量は、多くもなく、少なくもないため、製麺の難易度が低く、安定して量産できます。

多加水ラーメン(40%~)
40%以上の麺は、「多加水麺」として分類されます。多加水の麺は、太めに切り出されることが多いです。
しかし、細め~極太まで対応可能な万能麺でもあります。
モチモチとした存在感のある食感で、近年、多加水ラーメンの人気が出ています。
反面、水分量が多いため、製法に見極めが必要で、製麺の難易度も高めになっています。
また、多加水の中でも超加水ぎみに仕上げようとする場合、弊社が提唱する「熟成」が必要で、麺の状態を見極めることも必要になります。

まとめ
今回の記事では、ラーメンの材料や形状、水分量などの観点から、分類しました。
それぞれのカテゴリーやタイプの深掘りなどの解説は、これからの課題ですね。
ラーメンに関するお役立ち記事を発信していきます。
理想のラーメン作りでサポートが必要な場合、大和製作所までお気軽にお問い合わせください。
全国のドリームスタジオで、麺専門家が、あなたの自家製麺をサポートいたします。
自家製麺のイベントも開催していますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね!

_上半身のみ_resize-300x283.png)